育児がひと段落し、そろそろ薬剤師として復職を考えているけれど、「ブランクが長くて知識が追いつくか不安…」と感じていませんか?
医薬品の知識は日々アップデートされているため、復職前にしっかり準備をしておくことが大切です。
そこで、復職を目指す薬剤師ママにおすすめの書籍を紹介します。
基礎をおさらいできる本から、最新の情報を学べる本まで、役立つ一冊を見つけて復職準備を万全にしましょう!
※こちらのページの画像は、クリックすると楽天市場の詳細ページが確認できるようになっています
薬剤師が復職前に読むべき必須本2つで【ブランクを埋める!】


今日の治療薬


内容
『今日の治療薬』は、医療従事者にとって欠かせない実用的な薬剤情報の集大成です。
書籍版とアプリ版が用意されており、毎年の改訂によって最新の医薬品情報が常にアップデートされています。
特にアプリ版は、新薬の承認や適応拡大、薬価改定といった最新情報を随時反映し、現場で即座に活用できる設計になっています。
この書籍は、大きく分けて「解説」と「便覧」の二部構成になっていて、
「解説」では疾患ごとの治療指針が示され、どのような薬剤が適しているのかが分かりやすくまとめられています。
一方の「便覧」では、臨床で必要な薬剤の詳細情報が一覧化され、薬効や副作用、用法用量まで詳しく記載されています。
収録されている薬剤の範囲も広く、感染症治療薬や抗悪性腫瘍薬、循環器系・神経系の薬など、あらゆる診療科の医療従事者が活用できる内容になっています。
アプリ版では、薬剤名や適応症での検索機能はもちろん、併用禁忌チェックや同効薬の比較機能が備わっており、必要な情報を素早く入手できる点が魅力!
2025年版では、新たに「簡易懸濁の可否情報」が追加され、併用薬比較機能も強化されました。
また、オーソライズド・ジェネリック(AG)についての情報も充実し、より精度の高い薬剤選択が可能になっています。
こうした改訂により、臨床現場での判断をサポートし、より適切な医療提供を支援する一冊となっています。
口コミ
『今日の治療薬』書籍版は、 医療現場で即戦力となる一冊 として、多くの医療従事者から高く評価されています。
特に、 収録されている薬剤の網羅性 は群を抜いており、日常診療での処方や薬の確認に役立つとの声が多く見られます。
疾患ごとの解説が便覧形式で整理されているため、 知りたい情報をすぐに探せる 点も好評のようです。
また、 毎年改訂されることで、最新の医薬品情報が反映される のも、この書籍の大きな強み。
医療は日々進化し、新薬の登場や処方の変更が頻繁に行われるため、 常に最新の情報を得られる 信頼性の高さは、多くの医師や薬剤師に支持されています。
B6判サイズでコンパクトなため、 現場で素早く確認できる という実用性が評価されています。
さらに、 疾患別・薬効群別に整理された構成 になっているため、直感的に使いやすい点も好評です。
一方で、 価格の高さ に関しては賛否が分かれます。
毎年改訂されるため、新しい版を購入し続けることに負担を感じるという意見もあります。
また、 情報量の多さ が初心者にはややハードルになるという指摘も。
全ての情報を把握するのは容易ではなく、特に医学生や研修医にとっては「最初は使いこなすのが難しい」との声もあります。
近年では、 電子版の利便性を支持する意見も増えており、検索機能がない書籍版に不便を感じる人もいる ようです。
無料オンライン付録の「e-OMAKE」では製剤写真や薬価が見られるものの、 電子版と比べて利便性の面では劣る という評価もあります。
それでも、 医療従事者にとって信頼できる情報源としての価値は揺るがない というのが、多くの読者の共通した意見です。
服薬指導のツボ 虎の巻


内容
『服薬指導のツボ 虎の巻』は、薬剤師の実務に直結する実践的な服薬指導ガイドブックです。
薬局で日常的に遭遇する27の主要疾患について、具体的な指導方法を詳しく解説。
初回投薬時から再投薬時まで、患者とのやり取りに役立つ知識が詰まっています。
この書籍の大きな特徴は、服薬指導を 「禁忌疾患の確認」「併用薬・飲食物・嗜好品の確認」「病識・薬識を持たせる」「注意事項(副作用など)の説明」 という4つのステップに分けて整理している点です。
この体系的なアプローチにより、指導の抜け漏れを防ぎつつ、患者が納得しやすい伝え方を身につけることができます。
さらに、 「説明例」 を豊富に収録しているのもポイント。
難しい医療用語を避け、患者が理解しやすい比喩や言い回しを取り入れることで、より伝わる服薬指導が可能になります。
また、 フルカラーのイラスト集 も付属しており、視覚的に説明を補うことで、より分かりやすく伝えることができます。
第3版では、新たに 不整脈、心房細動、心不全といった循環器疾患 に関する服薬指導が追加され、より幅広いケースに対応。
併用薬や相互作用に関する最新情報も盛り込まれており、最新の知識を現場で即活用できます。
服薬指導は、単に薬を渡すだけでなく、患者が正しく理解し、安心して治療を続けるための重要なコミュニケーションの場!
『服薬指導のツボ 虎の巻』を活用すれば、より分かりやすく、より納得感のある指導ができるようになるはずです。
口コミ
『服薬指導のツボ 虎の巻』は、薬剤師の実務に即した内容で、多くの読者から好評を得ています。
その魅力の一つは、 内容の充実度と実用性の高さ。
特に 「説明例の豊富さ」 は、多くの薬剤師にとって役立つポイントの一つです。
患者に伝わりやすい言葉選びや比喩がふんだんに盛り込まれており、そのまま現場で活用できる実践的な内容になっています。
また、 薬局でよく遭遇する27の主要疾患をカバー しているため、「必要な情報がコンパクトにまとまっていて使いやすい」との声も多く聞かれます。
循環器疾患(不整脈、心房細動、心不全)が追加 され、より幅広い疾患に対応できるようになった点も評価のポイント。
日々の業務で即戦力となる情報が満載です。
一方で、 価格がやや高め という意見もありますが、「内容の充実度を考えると十分価値がある」との評価が多く、満足度は総じて高い印象です。
今後の改訂でさらに対応疾患が増えることを期待する声もあり、進化を続ける参考書として注目されています。
薬局ですぐに役立つ薬の比較と使い分け100


内容
『薬局ですぐに役立つ薬の比較と使い分け100』は、 現場の薬剤師が即戦力として活用できる一冊 です。
日々の調剤業務や服薬指導、疑義照会の際に、「この薬とあの薬の違いは何だろう?」と迷うことありますよね!?
この書籍では、 約730点もの参考文献を基に、類似薬の違いを分かりやすく解説 しています。
単なる成分や作用機序の比較だけでなく、 医師が処方を選ぶ意図 まで掘り下げて説明されているため、患者さんへの説明や処方提案にも役立ちます。
本の構成は、 疾患ごとに薬剤を比較し、その使い分けを詳しく解説するスタイル 。
例えば、循環器系では 「クレストールとリピトールの違い」 や 「ワーファリンとバイアスピリンの使い分け」 など、実際の処方でよく目にする組み合わせをピックアップ。
さらに、解熱鎮痛薬では 「ロキソニンとカロナール」、呼吸器系では 「アドエアとシムビコート」 など、各分野で混同しやすい薬剤について詳しく比較しています。
精神神経系や泌尿器系、さらには外用薬まで幅広くカバーされており、 「デパスとソラナックスの違い」 や 「ヒルドイドとパスタロンの使い分け」 など、知っておくと現場で即活用できる情報が満載です。
特に、 「単に薬の違いを知るだけでなく、患者さんにどう説明すればいいか」 という視点が盛り込まれているのが本書の特徴。
例えば、便秘薬のマグミットとプルゼニドの違いを説明する際、単に「マグミットは塩類下剤で、プルゼニドは刺激性下剤」と伝えるだけではなく、 「マグミットはゆっくり効くので予防向き、一方でプルゼニドは即効性があるけれど常用には向かない」 など、患者さんが納得しやすい伝え方のヒントも得られます。
薬剤師が日々の業務で直面する疑問を解決し、より的確な服薬指導につなげる ための実践的な内容が詰まっている書籍です!おすすめ!
口コミ
『薬局ですぐに役立つ薬の比較と使い分け100』は、多くの薬剤師から 「実践ですぐに役立つ!」 と高評価を受けている一冊。
特に 内容の分かりやすさと実用性の高さ が好評で、「類似薬の違いが一目で分かる」「処方の意図を理解しやすくなった」といった声が寄せられています。
この本の魅力は、 豊富なエビデンスをもとにした解説 です。
漠然とした説明ではなく、 「なぜこの薬が選ばれるのか?」 という視点で書かれているため、薬局や病院の現場でそのまま活用できる内容になっています。
「処方提案や服薬指導に自信が持てるようになった」という口コミも多く、 新人薬剤師やブランクのある薬剤師 にとって心強いサポートになることは間違いありません。
また、 研修医や看護師、薬学生の実務実習にも役立つ という意見もあり、薬剤師以外の医療従事者にも支持されています。
「復職前の勉強にちょうどいい」「患者さんへの説明がスムーズになった」といった感想も見られ、学習ツールとしても高い評価を得ています。
一方で、 サイズが大きく、持ち運びには不便 という声や、 「一部の内容がやや浅く感じる」という指摘 も。
しかし、その点についても「自己学習のきっかけになる」「分かりやすさを重視しているからこそ」と納得する声が多いようです。
価格についても「少し高めだが、内容を考えれば妥当」と評価されているようです。
総じて、『薬局ですぐに役立つ薬の比較と使い分け100』は、 現場の疑問をすぐに解決できる、実務に直結した一冊!
特に 新人薬剤師や復職を考えている薬剤師 にとっては、 「読んでよかった!」 と思える内容になっていると思います。
【基礎から最新知識まで】復職前にチェックしたい薬剤師向け書籍リスト
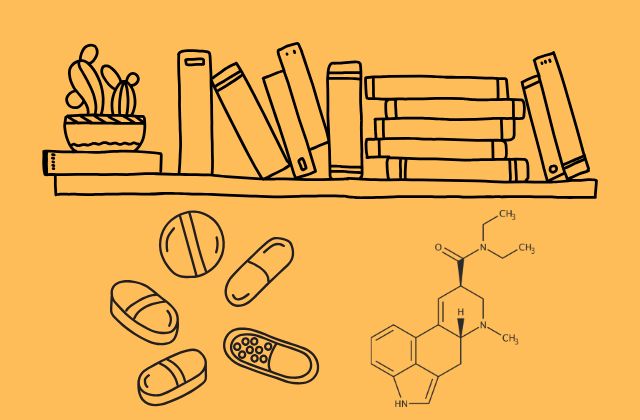
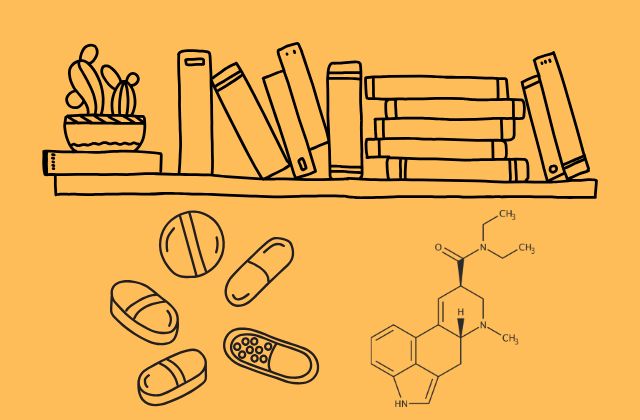
薬がみえるシリーズ


内容
『薬がみえる』シリーズは、 「薬をもっと分かりやすく、もっと実践的に学べる」 をコンセプトにした医療従事者向けのビジュアルテキストです。
薬の解説だけでなく、 解剖生理や疾患の成り立ち、治療法まで幅広く網羅 されており、 医師、薬剤師、看護師、薬学生など幅広い層に支持されています。
シリーズは Vol.1〜3の各論編とVol.4の総論編 に分かれており、各巻ごとに 主要な疾患と治療薬の知識を体系的に学べる構成 になっています。
特に イラストが豊富 に使われているため、 視覚的に理解しやすいのが大きな特徴 です。
文字だけの解説ではピンとこなかった薬の作用機序も、 一目でイメージしやすく、臨床現場での応用につなげやすい という声が多く寄せられています。
Vol.1では、神経系・循環器系・腎・泌尿器系の疾患と薬を解説。
第2版では 新たに漢方薬の項目も追加 され、より実践的な内容へと進化しています。
さらに、 2021年11月4日に発売された第2版では最新の医薬品情報や疾患情報が反映 され、 今後もVol.2以降の改訂が予定されている など、常に最新の医療情報を提供しているのも魅力のひとつです。
このシリーズの強みは、 薬理と疾患の関連性を明確に示していること です。
単なる暗記ではなく、「なぜこの薬が使われるのか?」という視点で学ぶことができるため、 服薬指導や治療提案の理解が深まる だけでなく、 現場で即戦力となる知識が身につく というメリットがあります。
『薬がみえる』シリーズは、 医療現場で実践的に使える知識をしっかり学びたい人にぴったりの教材 です。
学習をサポートするだけでなく、臨床の現場でも役立つ一冊 として、多くの医療従事者に愛用されています!
口コミ
『薬がみえる』シリーズは、多くの医療従事者や学生から 「とにかく分かりやすい!」 と高評価を得ているビジュアルテキストです。
特に、 フルカラーの図解やイラストが豊富 で、 薬の作用機序や疾患の病態が視覚的にスッと頭に入る という点が人気の理由になっています。
「文字ばかりの教科書だと理解しにくいけど、これは図解で説明されているから直感的に覚えられる!」 という声も多く、 試験対策や実務の知識整理に最適な一冊 だと評判です。
また、 生理学・病態・薬理が一つにまとまっている ので、 基礎から臨床までをしっかり結びつけて学べる のも魅力の一つ。
国試対策や、ブランクがある人の復職時の学び直しにも活用しやすい一冊です。
さらに、「医学書にしては 手頃な価格で内容が充実 しているからコスパが良い!」という評価もあり、学生や研修医、現場の医療従事者まで幅広い層に支持されています。
一方で、 「本が大きくて重いので持ち運びが大変」 という意見や、 「初学者には十分だけど、専門的な細かい部分まではカバーしきれていない」 という声も。
電子版を希望する人も少なくないようです。
総じて、『薬がみえる』シリーズは 「わかりやすさ」「実用性」「コストパフォーマンス」 の3拍子がそろった参考書として、医療系の学習に欠かせない存在になっています。
試験勉強から臨床現場まで幅広く役立つ ので、薬を学ぶすべての人におすすめです。
図解入門よくわかる薬理学の基本としくみ


内容
『図解入門 よくわかる 薬理学の基本としくみ』は、 薬理学の基礎をやさしく解説 した入門書です。
専門的な知識がなくても理解しやすい構成になっており、 医学生・看護学生・薬学生はもちろん、一般の読者にも役立つ内容 になっています。
本書の大きな特徴は、 視覚的なわかりやすさ。
フルカラーの図やイラストが豊富 で、薬の作用機序や病気の発生メカニズムを 直感的に理解 できるよう工夫されています。
薬の名前をズラッと並べるのではなく、「〇〇系」といった 大まかな分類で解説 しているので、 全体像をつかみやすい のもポイントです。
内容は 全16章構成 で、 薬の基本概念(第1~4章)、 薬の作用と用法(第5~7章)、 各種疾患と関連する薬(第8~15章)、 市販薬とサプリメント(第16章)と、体系的に学べるようになっています。
具体的なトピックとしては、 自律神経系・心臓・血圧・消化器系・呼吸器系 など、幅広い疾患と薬の関係をカバー。
さらに、 抗生物質・抗不安薬・睡眠薬・糖尿病治療薬・麻酔薬 など、医療現場で重要な薬についても詳しく解説されています。
「薬理学は難しそう…」と思っている人でも、この本なら スムーズに学習を進められる はず。
口コミ
『図解入門 よくわかる 薬理学の基本としくみ』は、 わかりやすく、読みやすい薬理学の入門書 として高評価を得ています。
特に 専門的な知識がない人でも理解しやすい という点が、多くの読者から支持されています。
本書の魅力は、 難解な内容を噛み砕いて解説 していること。
薬の名前を覚えるのではなく、「〇〇系」といった 大まかな分類で整理 されているため、 直感的に理解しやすい という声が多く見られます。
また、 病気や症状の発生メカニズム、薬の作用機序が丁寧に説明 されているため、 「なぜそうなるのか?」がしっかり腑に落ちる という点も好評です。
さらに、 フルカラーの図やイラストが豊富 で、視覚的に理解しやすいのもポイント。
文字ばかりの参考書は苦手…という人でも、楽しみながら学べる との口コミが多く寄せられています。
対象読者は 医学生・看護学生・薬学生 だけでなく、 一般の読者にも役立つ との意見が多く、 「薬のことを知りたいけれど、専門書は難しすぎる…」という人にもぴったり という声が目立ちます。
初学者が薬理学を学ぶための一冊として最適 であり、 「薬理学が楽しくなる本」 という評価も多く見られます!
謎解きで学ぶ薬学生・新人薬剤師のための処方解析入門


内容
『謎解きで学ぶ 薬学生・新人薬剤師のための処方解析入門』は、 処方解析を実践的に学べる入門書 です。
「なぜこの薬が処方されたのか?」 という疑問を解き明かしながら、投薬のポイントや処方箋の読み方を身につけられる構成になっています。
本書の最大の特徴は、 謎解き形式で学べる こと。
単なる知識の羅列ではなく、 実際の処方例を題材にして考えながら学ぶ ため、臨床の現場ですぐに役立つ実践力が身につきます。
例えば、 糖尿病患者の低血糖リスク や COPD患者への投薬の注意点、 抗悪性腫瘍薬の投与量の確認 など、 薬剤師として知っておくべき重要なテーマ が取り上げられています。
さらに、 「処方箋を読む」だけでなく、「患者さんへのアプローチ方法」まで学べる のもポイント。
薬の選択理由や相互作用だけでなく、 患者さんにどのように説明すればよいのか?どんな質問をすればよいのか? といった実践的なスキルまで網羅されています。
なので、 薬学生や新人薬剤師向け に作られていますが、 現場経験のある薬剤師が復習として読むのにも最適 です。
現在、 改訂第3版が発売中 で、最新の情報もカバーされています。
処方解析を基礎から実践までしっかり学びたい人、患者さんによりよい説明ができる薬剤師を目指したい人に、ぜひおすすめしたい一冊です。
口コミ
『謎解きで学ぶ 薬学生・新人薬剤師のための処方解析入門』は、 「楽しく学べて、実践的に役立つ」 と好評の一冊です。
特に評価されているのは、 謎解き形式で学習できる点。
処方解析を 単なる暗記ではなく、考えながら学べる ため、自然と実践的な力が身につくと評判です。
実際の処方箋を題材にしているので、 現場でそのまま役立つ知識が得られる のも大きなポイント。
また、 基礎から応用までしっかり学べる という声も多く、処方箋の読み方だけでなく、 患者さんへのアプローチ方法 まで詳しく解説されている点が高く評価されています。
「教科書的な内容にとどまらず、 現場でよく遭遇する処方例を扱っている ので、すぐに実務に活かせる」との意見も。
特に 薬学生や新人薬剤師にとって、処方解析を学ぶ入門書として最適 との声が目立ちます。
難しすぎず、それでいて実用的な知識が身につくため、 薬剤師としてのスタートを支えてくれる一冊 になっているようです。
さらに、 改訂が進んで最新の情報が反映されている 点も安心材料。
現在、第3版まで改訂されており、「古い知識ではなく、今の現場に即した内容が学べる」と好評です。
総じて、「処方解析の勉強って難しそう…」と感じている人にこそおすすめしたい本です。
楽しみながら、実務に直結する知識を身につけたい人にはピッタリの一冊 !
薬剤師の復職後に役立つスキルとは?読んでおきたい実践向け書籍
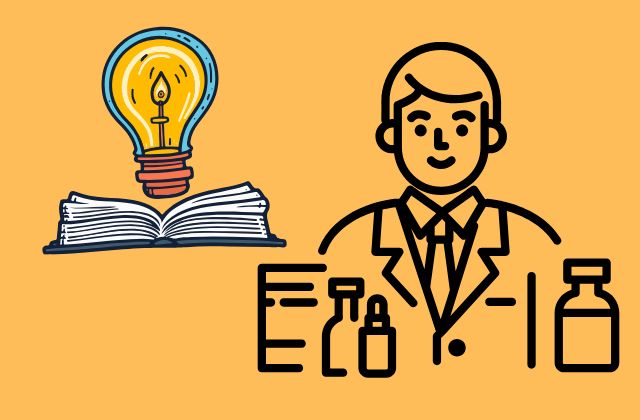
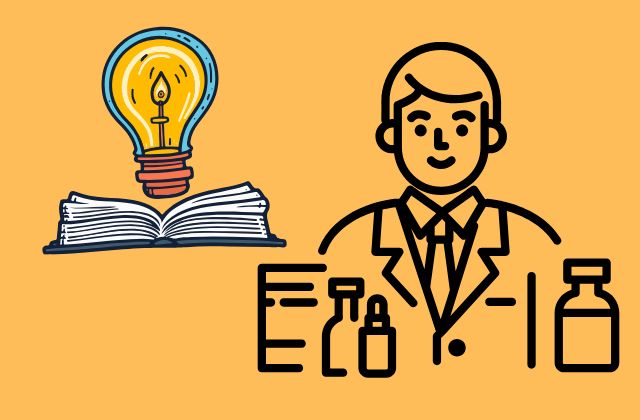
実践薬学


内容
『薬局で使える実践薬学』は、 薬剤師として現場で活かせる知識を身につけるための一冊 です。
単なる薬の暗記ではなく、「なぜこの薬が選ばれるのか?」「どのように患者さんへ説明すべきか?」といった 実践的な視点 を養うことが目的になっています。
本書の特徴は、 1年間の月別テーマ に沿って、薬局で役立つ知識を整理して学べる点。
例えば、 睡眠薬の分類と服薬指導 では、それぞれの薬の特性を踏まえ、患者さんごとの適切な説明方法がわかります。
また、 薬物動態学の実践的理解 や CYPが関与する相互作用 など、薬剤師に欠かせない専門知識も、現場目線で詳しく解説。
さらに、 NSAIDsの適切な使用 や PPIの比較と使用法 など、日常業務でよく直面する処方薬の選び方についても詳しく説明されています。
「どの薬をどう使い分けるべきか?」が明確になるため、 患者さんからの質問にも自信を持って答えられる ようになるでしょう。
また、本書のもう一つの魅力は、 実際の薬局での経験を基にした解説 です。
著者がひのくにノ薬局の勉強会形式で、 若手薬剤師の視点を交えながら実践的な活用法を紹介 しているため、「学んだけど実務でどう使えばいいかわからない…」という悩みを解決するヒントが満載。
特に 若手薬剤師や薬学生 にとっては、現場のリアルな疑問に寄り添った実践書として、 明日からの業務にすぐ役立つ知識を得られる 一冊になっています。
薬学部で学んだ知識を、 現場でしっかり活かせる力をつけたい人にぴったり の内容です。
口コミ
『薬局で使える実践薬学』は、 現場で即戦力になる知識が詰まった一冊 として、多くの薬剤師から高く評価されています。
特に、 日々の業務で直面する疑問を、実践的な視点で解決できる 点が好評です。
「添付文書を読んでも分からなかったことが、この本では実務ベースで解説されていて、すぐに使える!」といった声が多く、 服薬指導や処方監査の質を高める ための参考書として重宝されています。
また、 月ごとのテーマ に沿った勉強会形式の構成が分かりやすく、「ただ情報を詰め込むだけでなく、考え方が身につく」「学んだことがそのまま業務に活かせる」といった意見も。
睡眠薬やNSAIDs、CYP相互作用、腎機能チェックなど 幅広いテーマを扱っている ため、実務経験の少ない若手薬剤師や薬学生にとって、 現場で自信を持って判断できる力を養える 内容になっています。
一方で、価格については「やや高め」という指摘があるものの、「情報量を考えれば納得できる」という意見も見られます。
また、「内容が濃いので、一度にすべてを吸収するのは難しい」との声もあり、 何度も読み返して使う前提の本 と言えそう。
さらに、電子版の提供を望むユーザーもおり、今後の改善が期待されるポイントとなっています。
総じて、『薬局で使える実践薬学』は 実務に即した知識と考え方を学べる実用書 として、高い評価を得ています。
特に 若手薬剤師や薬学生にとって、現場のリアルな疑問に答えてくれる一冊!
薬局栄養指導


内容
薬局での栄養指導は、 ただ「食事に気をつけてください」と伝えるだけではなく、患者さんの生活に寄り添い、具体的なアドバイスを提供する ことが大切です。
本書では、 栄養学の基礎 から 疾患別の指導法、実践的なカウンセリングスキル まで、薬剤師や管理栄養士が現場で活かせる知識を詳しく解説しています。
まず、 栄養学の基礎 では、1日の食事回数や摂取すべき栄養素について学び、 タンパク質の摂取源や野菜の適切な摂取量、ベジタリアンの栄養管理 など、 年齢やライフスタイルに応じた食事の考え方 を身につけることができます。
さらに、 誤嚥や低栄養への対応 についても触れ、 高齢者や嚥下機能が低下した方への実践的なアドバイス も学べます。
また、 病気と食品の関係 についても詳しく解説。
例えば、 関節リウマチの症状を悪化させる食品 や 痛風患者にとっての適切な飲酒の仕方、さらには 抗血小板薬と納豆の相互作用 など、 薬と食事の関係を正しく理解し、適切な指導ができる力 を養います。
熱中症対策や特定の食品と健康の関係 についても紹介されており、季節ごとの指導にも役立ちます。
さらに、 慢性疾患の栄養指導 では、 脂質異常症・高血圧・骨粗鬆症・肥満症などの疾患別に、具体的な食事アドバイスを提案。
「何を食べてはいけないか」だけでなく、「どう工夫すればおいしく、楽しく食べられるか」 という視点を大切にしています。
そして、 薬局での栄養指導の実践方法 についても詳しく解説。
患者さんの本音を引き出す質問技術や、管理栄養士との連携、多職種と協力した栄養指導の進め方 など、現場で即使えるスキルを学ぶことができます。
薬局での特定保健指導の進め方 についても触れられており、 より効果的な健康支援の方法 を知ることができます。
最後に、 33種類の疾患・症状対応レシピ を掲載。 「食事指導はしたけれど、何を作ればいいかわからない…」という患者さんに、自信を持って提案できるレシピ がそろっています。
この本は、 薬剤師や管理栄養士が「患者さんの健康を食事から支える力」をつけるための実践的なガイド です。
「食と薬」をつなげる視点を身につけ、より質の高い栄養指導を行いたい方にとって、心強い一冊 。
口コミ
『今日から使える薬局栄養指導Q&A』は、 薬局での栄養相談にすぐ活かせる実用的な一冊 として、多くの読者から高評価を得ています
。特に、「相談者が本当に知りたいことに焦点を当てている」との声が多く、 現場で役立つ具体的なアドバイス が満載だと評判です。
この書籍の大きな魅力のひとつは、 専門家による信頼性の高さ。
管理栄養士と医師が監修しているため、根拠に基づいた栄養指導が学べる 点が支持されています。
薬局での栄養指導は、単なる「食事のアドバイス」にとどまらず、 薬や疾患との関係をしっかり理解した上での指導が求められる ため、こうした専門的な視点があることは大きな安心材料です。
また、 Q&A形式のわかりやすい構成 も好評で、「必要な情報をサッと探せるので便利」「読みやすくて実践しやすい」との声が寄せられています。
病態栄養の理論を最小限にとどめ、 薬局での実践に直結する内容がコンパクトにまとまっている ため、忙しい現場でもすぐに活用できると評価されています。
さらに、 対象読者が広い のも特長のひとつ。
薬剤師や管理栄養士だけでなく、 薬局スタッフ全般にとって有益な内容になっている ため、「スタッフみんなで共有して使える」といった口コミも見られます。
最新情報がしっかり反映されている点も、読者にとって大きなポイント。
2022年2月発行の比較的新しい書籍 ということもあり、 最新の栄養指導の知見が反映されている のも評価されています。
『今日から使える薬局栄養指導』は、 薬局での栄養指導を実践的に学びたい人にとって、まさに“今日から使える”知識が詰まった一冊。
デキる薬剤師をつくる現場の教科書


内容
薬剤師として現場で本当に役立つ知識を学びたいなら、この一冊。
『デキる薬剤師をつくる現場の教科書』は、新人薬剤師や若手薬剤師向けに 大学では学べない実践的なスキル を詳しく解説した教科書です。
本書は、 「基礎知識」から「日常業務の常識」 まで幅広くカバーしており、調剤技術、薬歴の書き方、添付文書の活用法、検査値の読み解き方など、 すぐに現場で使える実用的な情報 が満載。
さらに、 一包化・粉砕ができない医薬品の扱い や 麻薬・ジェネリック医薬品の管理 など、実際に直面する課題に対する具体的な対策も学べます。
また、薬剤師を取り巻く最新のトピックスも網羅。
薬局のDX化の動きや最新の医療制度 についても触れられており、今後の薬剤師の在り方を考える上でも役立ちます。
この本の大きな特徴は、 現場のリアルな声をもとに構成されている こと。
単なる理論ではなく、 179の「現場の常識」 を通じて、実際に業務で活かせる知識を学べるのがポイントです。
さらに、 eラーニングサイト『elephant for pharmacists』 と連携し、動画コンテンツを活用しながら学べるのも魅力。
2025年には 最新版「デキる薬剤師をつくる現場の教科書NEXT」 も発売されているので、そちらでは最新の知識をしっかりキャッチアップできます▼
⇒ JiMagazine(『調剤と情報』編集部が運営するWebメディア)でチェックする
口コミ
「新人薬剤師が最初に読むべき一冊」として高く評価されている『デキる薬剤師をつくる現場の教科書』。
実際に読んだ人たちの声をまとめると、 実用性の高さ・網羅性・教育的価値 という3つのポイントが際立っています。
まず、新人薬剤師からは「右も左も分からない状況で役立つオールインワンの書籍」として好評。
調剤技術から服薬指導、患者対応、保険制度まで 「浅く広く」学べる ので、効率的に知識を身につけられると評価されています。
特に 「現場の常識」をしっかり押さえた構成 になっているため、実際の業務で困ったときの「辞書」として活用する人も多いようです。
また、 若手薬剤師だけでなく、後輩指導をする中堅・ベテラン薬剤師にも役立つ という声も。
教育ツールとしての価値が高く、「新人にこれを読ませておけば、基本的なことはカバーできる」と指導者目線でも支持されています。
実践的な内容も魅力のひとつ。
検査値の見方や服薬指導のコツ、調剤過誤を防ぐポイント など、日々の業務に直結する知識が詰まっており、すぐに役立つと感じる人が多いようです。
一方で、 紙の質がやや安っぽい という指摘や、「広範囲をカバーしているため、専門性を深めるには追加の学習が必要」といった意見もあります。
ただし、こうした点を差し引いても 内容の満足度は非常に高い というのが大方の評価です。
総じて、『デキる薬剤師をつくる現場の教科書』は、新人薬剤師や若手薬剤師にとって 現場で即戦力となる知識を効率よく学べる一冊 です。
保険調剤Q&A


内容
調剤報酬の解釈や算定方法について 「知りたいことがすぐにわかる」 便利な一冊、それが 『保険調剤Q&A 令和6年版』 です。
日々の薬局業務で直面する疑問を Q&A形式 でわかりやすく整理しているため、 実務に直結する知識 をスムーズに学べます。
本書の最大の特徴は、 令和6年度の調剤報酬改定に完全対応 している点。
調剤基本料や服薬管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料などの 最新の算定方法 を詳しく解説し、 現場のルール変更にも素早く対応できる ようになっています。
また、「マイナ保険証」や「オンライン資格確認」など、近年の デジタル化の流れに関する最新情報 もカバー。
制度の変化に対応するための 実践的なポイント が押さえられています。
さらに、 過去20年分の疑義解釈通知を整理した資料編 も充実。
調剤報酬の算定根拠をすぐに確認できるので、 「この加算はどう適用される?」といった疑問をスピーディーに解決 できます。
具体的なトピック には、
- 処方箋受付時の注意点
- 疑義照会の対応方法
- 麻薬の取り扱いルール
- 後発医薬品調剤体制加算の詳細
- 訪問薬剤管理指導のポイント
など、 現場の薬剤師が知っておくべき必須の知識 が網羅されています。
忙しい現場でサッと確認できる「実践の手引き」 として、多くの薬局で活用されている本書。 日々の業務をスムーズに進めたい薬剤師の強い味方 になること間違いなしです。
口コミ
「すぐに役立つ!」「情報がまとまっていて助かる!」 など、現場の薬剤師や薬局スタッフから高評価を得ている 『保険調剤Q&A 令和6年版』。
調剤報酬の 解釈や算定方法がQ&A形式で整理されている ため、知りたい情報をすぐに見つけられるのが好評のポイントです。
特に評価が高いのは 実用性の高さ。
- 調剤報酬改定の最新情報 を網羅しているので、制度変更にもスムーズに対応できる
- 疑義解釈通知が充実 していて、算定根拠をすぐに確認できる
- 「マイナ保険証」や「オンライン資格確認」など最新トピックス もカバーされている
「忙しい薬局業務の中で、すぐに正しい情報を確認できるのがありがたい」という声が多く、実務に直結する書籍として 日常業務に欠かせない一冊 になっています。
また、Q&A形式の構成 も「知りたいことにすぐアクセスできる!」と好評。
注意すべきポイントが明確になっているので、時間のない現場でも活用しやすい との意見が寄せられています。
一方で、一部のユーザーからは 「専門的な内容が多く、初学者には少し難しい」 という声や、 「電子版があればもっと便利」 という要望も見られます。
とはいえ、 現場で役立つ実践的な書籍としての評価は非常に高く、調剤業務をスムーズに進めるための必携書 であることは間違いありません。
「調剤報酬の疑問をサクッと解決したい」「最新の改定情報をチェックしたい」そんな方に、まさにぴったりの一冊 です!
忙しい薬剤師ママ必見!書籍以外のスキマ時間で学べる勉強法とおすすめツール


m3.com
m3.comは、薬剤師のスキルアップや日常業務に役立つ情報を提供する医療従事者向けの情報サイト です。
26万人以上の薬剤師が利用 しており、最新の医療情報や研修機会を得るための強力なプラットフォームとなっています。
薬剤師向けの充実したコンテンツ
m3.comの魅力は、実務に直結する情報が豊富なこと。
- 調剤や服薬指導に役立つ最新情報 を配信
- 認定薬剤師の資格取得・更新 に必要な研修情報が充実
- 疑義照会や医師とのコミュニケーションのコツ など、実践的なコラムも多数掲載
学びを深める研修・eラーニング
「研修を受けたいけど、どう探せばいい?」という方にも便利な機能が揃っています。
- 認定薬剤師ナビ で、テーマや開催地ごとに研修を検索可能
- m3ラーニング では、自分のペースで学べるeラーニング講座を提供
さらに、研修会の参加申込フォームを無料で作成できるサービス もあるので、研修主催者にとっても便利なサイトです。
薬剤師の「知りたい」をサポート
日々の業務で直面する課題に役立つ情報も満載。
- 実務に関するコラムや特集記事 を定期的に配信
- 患者さん対応や服薬指導のポイント など、実践的なノウハウを学べる
「最新の医療情報をキャッチしたい」「スキルアップしたい」「研修情報を探したい」 そんな薬剤師の強い味方となるのが m3.com。
無料ですし、日々の業務の質を向上させるために、ぜひ活用を!
DIオンライン&日経メディカル
日経BPが運営する医療従事者向けの総合情報サイト。
薬剤師や医師に向けて、 臨床情報・行政動向・病院経営 など幅広い分野の最新ニュースや専門的な知見を発信しています。
圧倒的な会員数と支持
この2つのサイトは、医療業界の多くのプロフェッショナルに利用されています。
- DI Online(薬剤師向け): 会員数16万人以上 → 日本の薬剤師の約半数が活用!
- Nikkei Medical Online(医師向け): 会員数20万人以上 → 30〜50代の現役医師から高い支持
信頼できる情報と専門性
日経BPが運営するだけあって、 情報の質の高さは折り紙付き。
- 独自取材によるニュースや特集記事 を提供
- 「日経ドラッグインフォメーション」の専門記者 による正確な記事編集
- 厳格な医師認証システムを導入 し、医療者向けの信頼性の高い情報を発信
臨床から経営までカバーする豊富なコンテンツ
「医療の最新動向を知りたい」「臨床の現場で役立つ情報がほしい」そんなニーズに応えるため、次のような内容を提供しています。
- 薬剤師向け:「最新の薬剤情報」「行政の動き」「服薬指導のポイント」
- 医師向け:「診療の現場レポート」「病院経営のノウハウ」「医療政策の解説」
さらに、 Web講演会やeディテール を通じた製薬企業の情報提供や、医師とMRが交流できる「日経メディカルLounge」 など、学びと交流の場としても活用されています。
利用者が増え続けている注目サイト
DI Onlineの月間閲覧数は 成長 を記録しており、ますます多くの医療従事者にとって欠かせない情報源となっています。
医療の最前線で働く人にとって、信頼できる情報を効率よく収集することは欠かせません。
DI Online&日経メディカルを活用して、最新の情報をキャッチし、復職までの知識の補充に役立ててみてください!
【復職成功のコツ】薬剤師ママが今からできる準備と勉強法!
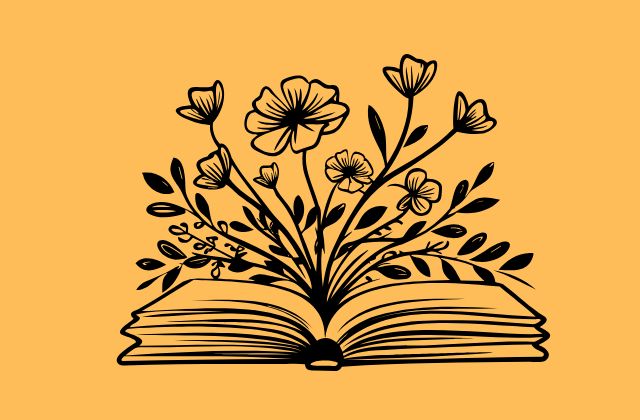
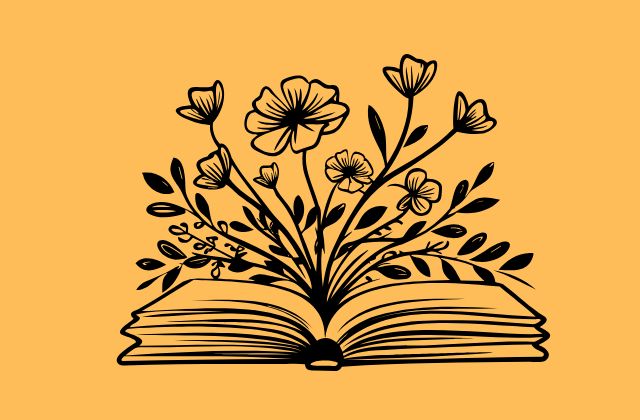
育児に追われる毎日から、「そろそろ復職したい」と考え始めても・・
ブランクが長くなるほど、「最新の薬剤情報についていけるか」「職場でうまくやれるか」など、不安を感じることもありますよね。
スムーズに復職するための準備と勉強法 とは!
1. 復職に向けた事前準備
まずは、無理なく仕事復帰できるように環境を整えておきましょう。
✅ 働き方のイメージを固める
「パートがいいのか、フルタイムにするのか」「調剤薬局か病院か」など、自分のライフスタイルに合った働き方を考えてみましょう。
✅ 家族の協力体制を作る
夫や両親と相談し、家事や育児の分担を明確にしておくと、復職後の負担が軽減されます。
✅ 保育園・学童の準備
子どもの預け先を早めに確保し、実際に通わせる練習をするのも大切。急な体調不良時の対応も考えておきましょう。
2. 仕事の勘を取り戻すための勉強法
薬剤師としてのブランクを埋めるために、少しずつ知識をアップデートしていきましょう。
📌 最新の薬剤情報をチェック
DI Onlineやm3.comなどの医療情報サイトで、新薬やジェネリック、処方のトレンドを把握しておきましょう。
📌 eラーニングを活用する
「m3ラーニング」や「認定薬剤師ナビ」など、薬剤師向けのオンライン研修を活用すれば、自宅で効率よく学べます。
📌 復職支援セミナーに参加する
調剤や在宅医療の最新動向を学べるセミナーもあるので、実際の業務をイメージしながら学ぶのがおすすめです。
📌 服薬指導のロールプレイ
患者さんとのコミュニケーションも重要な仕事の一つ。家族を相手に服薬指導の練習をするのも効果的です。
3. 自信を持って復職しよう!
復職に向けた準備を進めることで、不安は少しずつ解消されるはずです!
「ブランクがあるから…」と尻込みせずに、できることから始めてみることが大切です。
あなたの経験や知識は、きっと職場で必要とされています。
私と一緒に少しずつ準備を進めて、自信を持って復職を迎えましょう!
転職復職を考えてる薬剤師ママはこちら▼
「もう若くないし転職って難しいのかな…」「未経験の分野でも大丈夫?」そんなモヤモヤを抱えてる人、多いんじゃないでしょうか。
しかも「薬剤師は転職サイトなんて使わないほうがいい!」なんて噂まで耳にしたら、ちょっと不安になりますよね・・。
でも実際のところどうなの?
こちらのページでは、その噂の真相や、40代50代の薬剤師が転職サイトを選ぶときに見るべきポイント、未経験やブランクがあっても安心して使えるサイトをわかりやすくまとめています。ぜひチェックしてみてください!
まとめ
復職に向けた不安を解消するには、事前の学び直しがとても重要です。
こちらで紹介した書籍を活用しながら、知識を整理し、自信を持って復職に臨みましょう。
また、無理のないペースで学習を進めることも大切です。育児と両立しながら、少しずつでも知識を取り戻していけば、復職後もスムーズに業務に馴染めるはず♪
ぜひ、自分に合った一冊を見つけて、復職への一歩を踏み出してくださいね。
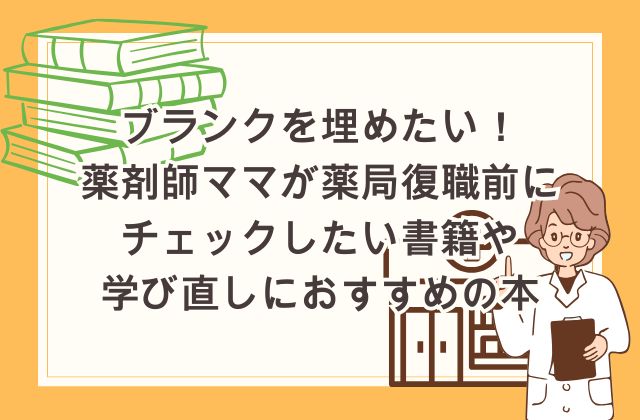












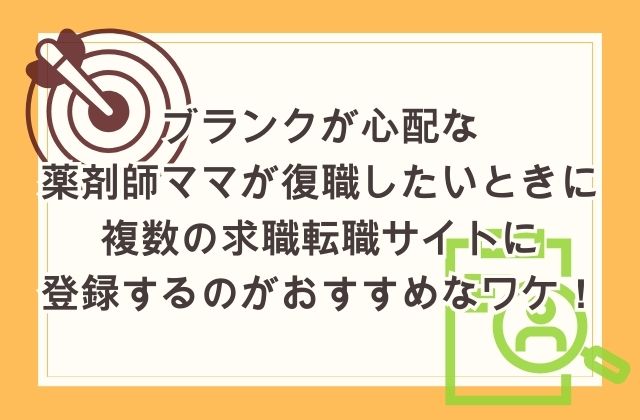
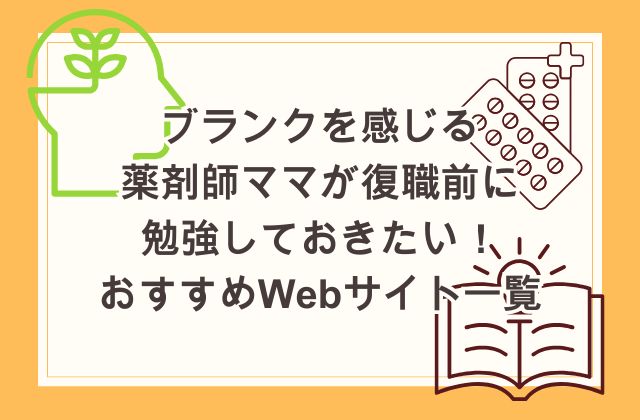
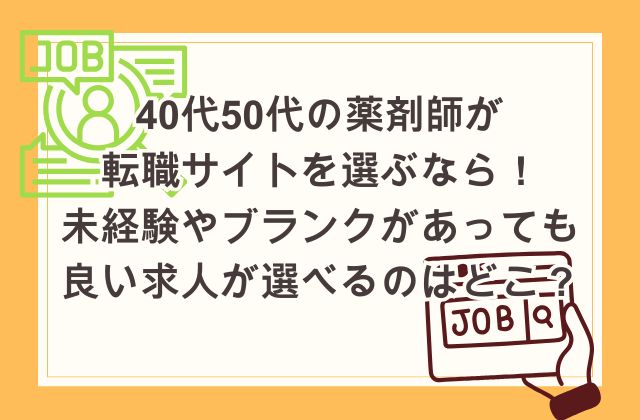
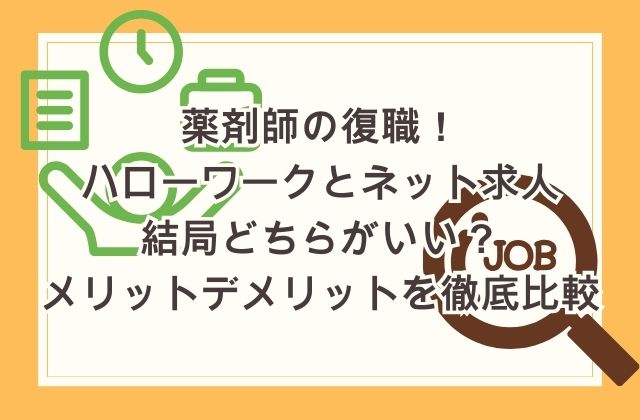
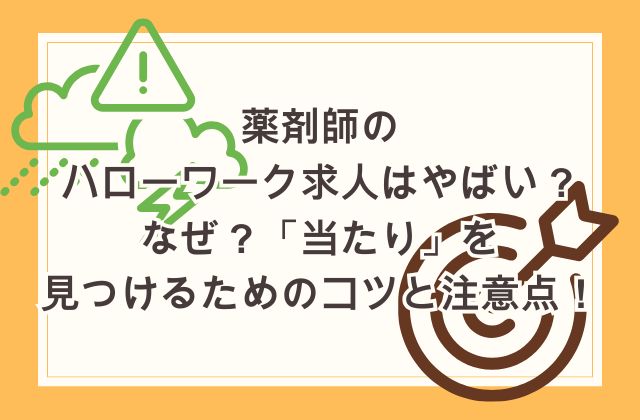
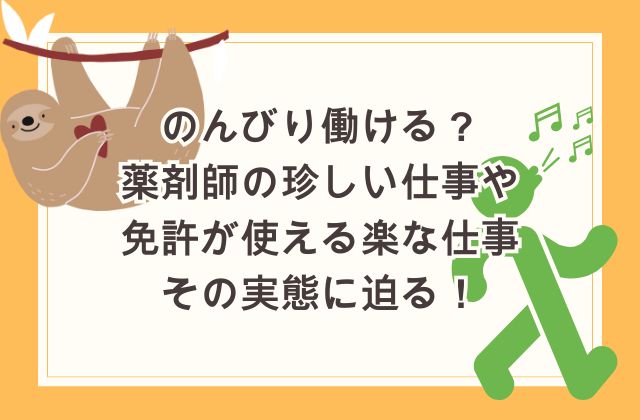
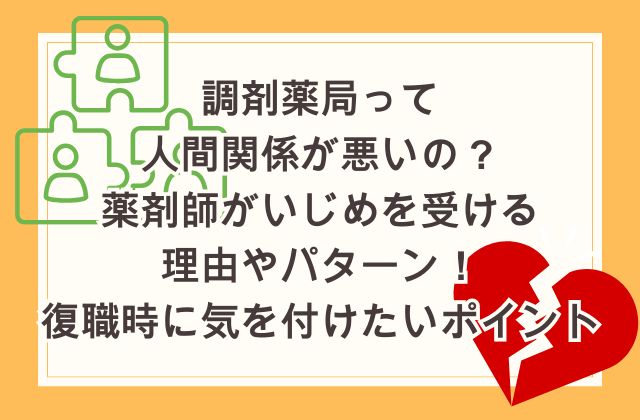
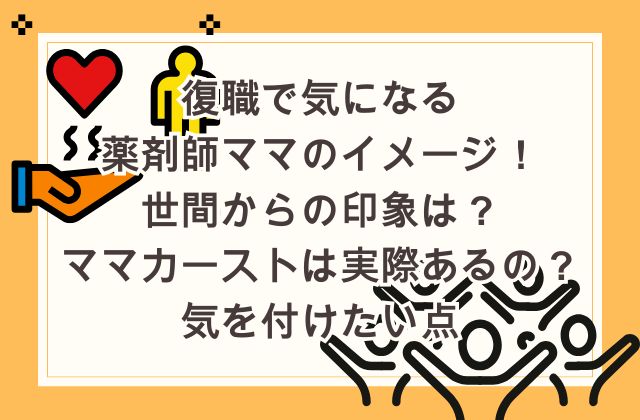
コメント